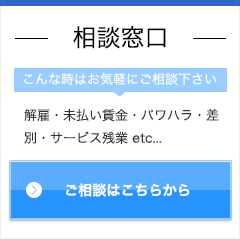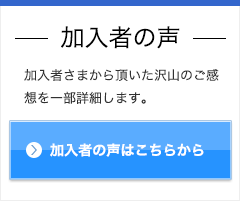【障害者を「弱者」と差別してないか】
2017年8月8日
朝日新聞
相模原市の「津久井やまゆり園」で19人の命が奪われた事件から、1年が経った。
犠牲者を追悼するため、メディアは「弱者を差別しない社会をつくろう」などと呼びかけるが、障害者の置かれている状況はむしろ悪くなっている――。
米国認定音楽療法士の佐藤由美子さんは「なぜ、アメリカでは障害者を『弱者』と呼ばないのか?」(7月31日)でそう記し、日米での違いを指摘する。
米国では、障害や病気のある人を「弱者」ではなく「バルネラブル(vulnerable)な人たち」と呼ぶと説明する佐藤さん。「バルネラブル」は直訳すると「脆弱(ぜいじゃく)な」などを意味するが、佐藤さんは「日本語にはない表現」だとして、「言葉の話せない国に行ったとき」や「風邪にかかったとき」など、障害の有無を問わず誰もが経験する状態だと記す。
障害者を「弱者」と分類して無意識に差別してはいないかと問い、最後に「私たちが目指すべき社会は、『弱者を思いやる社会』ではなく、『弱者をつくらない社会』だと思う」と訴える。
【なぜ、アメリカでは障害者を「弱者」と呼ばないのか?】
相模原殺傷事件が起きてから1年が経った。犠牲者を追悼するため、メディアは「弱者に思いやりを」「弱者を差別しない社会をつくろう」と呼びかける。しかし、障がい者の置かれている状況が変わる兆しは見えてこないばかりか、むしろ悪くなっている。
共同通信が全国の知的障害者の家族を対象に実施したアンケートでは、事件後、障害者を取り巻く環境が悪化したと答えた人が7割だった。
私は長年アメリカに住んでいるが、アメリカ人と日本人では障がいに関する考え方が大きく違う。そもそも英語では障がい者(disabled people)とは言わない。
障がいを持つ人、障がいと共に生きる人(people with disabilities)という言い方をする。
子どもの場合は、障がい児(disabled children)とは言わず、特別なニーズのある子ども(children with special needs)と呼ぶのが一般的だ。あくまでも「人」に焦点を当て、私たちには人間として同じ権利があることを強調する。そして、アメリカ人はそれを子どもの頃から自然に学んでいく。
「インクルージョン・クラスルーム」と言って、障がい児も健常児(typical children)も同じ学校に通う。障がいのあるすべての子どもたちが、健常児と同じように学ぶことができる「環境」を提供することは、公立学校の義務であると法律で定められているのだ。
教育だけではない。交通機関や公共機関へのアクセス、雇用や住居の機会均等が法律で守られており、世間一般では当然のこととして認識されている。
このような社会では、障がいや病気のある人を「弱者」とは呼ばない。もし、彼らを "weak people(弱者)"などと呼んだら、アメリカ人は間違いなく「差別だ」と言うだろう。もし、障がい者が「社会的弱者」であるとしたら、社会が変わる必要があると彼らは考えるのだ。
「弱者」の代わりに英語では、「バルネラブルな人たち(people who are vulnerable)」という言い方をする。日本語にはない表現で、「弱者」とも意味が違う。バルネラブルは、障がいの有無を問わず誰もが経験することだ。たとえば、言葉の話せない国に行ったとき、暗い夜道を一人で歩いているとき、風邪にかかったときなどには、バルネラブルな状態になり得る。
「弱者」という言葉が、(彼ら)と(私たち)を区別する言葉だとしたら、「バルネラブル」は、人間誰もが経験する苦しみや悲しみを通じて、私たちをつなぐ言葉である。
「障がい者」や「弱者」とそうでない人たちを、白黒で分けることはできない。あなたが今健康だとしても、病気や事故でいつ障がいをもつかわからないし、すべての人に死は訪れる。そして死期が近づいているとき、私たちは人生で最もバルネラブルな状態にあると言えるだろう。突然ポックリ死ぬことがない限り、確実に誰かの支えや助けが必要になる。
そのときあなたは何を求めるだろう? 弱者というカテゴリーに振り分けられ、「かわいそう」と思われたいだろうか? どうせもうすぐ死ぬのだからと、生きていても意味のない人間のように扱われたいだろうか?おそらくあなたは、体は弱っていても、人間として本質的な部分では変わっていないと感じるだろう。だから、ありのままの自分を受け入れて欲しいし、自分の気持ちをわかって欲しい、と願うと思う。これは、人間誰もが心の奥底で願っていることなのだ。
善意の人々からの浅い理解は、悪意の人々からの絶対的な誤解よりも苛立たしい。
キング牧師はそう言った。障がい者に対して悪意を抱いている人は少ないだろう。しかし、私たちの理解は深いと言えるだろうか? 彼らを「弱者」と分類し、無意識に差別してはいないか?私たちが目指すべき社会は、「弱者を思いやる社会」ではなく、「弱者をつくらない社会」だと思う。(2017年7月31日 HuffPost)
ユニオンからコメント
アメリカには、(障害児が健常児と同じ教室で学ぶ)「インクルージョン・クラスルーム」の環境があり、子どもの頃からそれを学んでいるので障害者や病人を「弱者」と呼ばない、というコラム記事です。
日本が批准した「障害者権利条約」の第24条(教育を受ける権利)は、「インクルージョン教育の実施」をすべての条約締結国に求めています。つまり、アメリカと同様、日本でも「インクルージョン教育」の実施を法律で定めていることが建前になっています。
「インクルージョン教育」については、障害の有無にかかわらず同じ教室で学ぶことの弊害を指摘する専門家もいます。健常者側からの懸念として、「異常行動による被害」「教師が障害者のケアに割かれ、結果的に教育の質の低下に繋がる」を掲げ、「障害児保護者の要望で、成人の介助者をつけるべき状況でも特定の健常児を世話係として教師が任命し日常的に介助している事例も多く、これが原因で障害者排除の思想を持つ生徒が生まれる懸念がある」としています。
つまり、障害のある子どもと同じ教室・隣の席になったことで、(教師からの圧力などで)やりたくないのに「お世話係」をさせられた。そう感じた子どもが、「迷惑をかけられた」「自分は損した」と感じてしまうことで障害者排除の思想を持ってしまうという懸念です。
また、障害者側からの懸念点として「一人だけ孤立する可能性がある」「障害者がいじめや嫌がらせに遭いやすい」「障害者に必要なスキルを十分に学べない。支援学校とは違い就職支援をしてもらえない」を挙げています。
杉山登志郎氏(精神科医:日本における高機能自閉症やアスペルガー症候群の権威)は、このような状況を「理解できない外国語で行われ、意見も求められるような会議に毎日8時間以上出席させるような状況」と例え、このような状況であれば障害者のためにならないと「インクルージョン教育」の問題点を指摘しています。
極端な言い方をすると、音楽療法士は何もかも一緒でなければだめだと説き、権威ある精神科医は何もかも一緒では弊害があると説いています。この論議は、障害者がはたらく職場に存在してしまう課題に通じるところがあります。
「障害者を弱者と分類し配慮することで、無意識に差別してはいないか?」
「双方のためには配慮が必要で、それがなければ障害者のためにもならない」
いずれにしても、日々を過ごす職場で悠長なことを言っていられません。社会が変わるのを待っていたり、懸念があると悩んだりしている時間は心の健康にも悪影響を与えます。
音楽療法士の筆者は、「善意の人々からの浅い理解は、悪意の人々からの絶対的な誤解よりも苛立たしい」という、人種差別反対運動で有名なキング牧師(Martin Luther King, Jr.:1929年1月15日~1968年4月4日)の言葉を引用しています。この一文は、実際に職場トラブルに悩む障害者から吐露される本音であり、抱えている感情の一つです。
非暴力的な指導者だったキング牧師とは対照的に、攻撃的な指導者として有名だったのがマルコム・X氏(Malcolm X:1925年5月19日~1965年2月21日)です。キング牧師と正反対のイメージを持たれていたマルコムX氏は次のような言葉を残しています。
「欲しいものがあるときは、ちょっとぐらいは騒ぎたてたほうがいいんだ」
障害者をどう呼ぶか、どのような社会が理想なのか、その議論の前に障害者が自ら声を上げることも大切です。障害者が職場で少数派であり、孤独を抱えがちなことは現実です。しかし、「積もりに積もって爆発してから」ではなく、「おかしい」と感じたとき、勇気を出してすぐに声を上げることでしか伝わらないことが少なくありません。
出典元:朝日新聞・HuffPost